農村の変貌
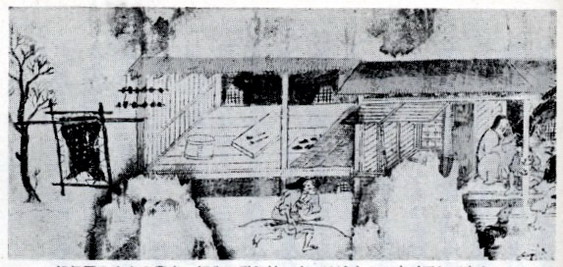
前8世紀末より律令制の規制は徐々に崩れており、編戸された本籍地から離れる浪人も、国司子弟・王臣子孫の国内居住も進んでいきます。そしてそれら王臣子孫も含めた有力農業経営者(当時の言葉で言うと「富豪の輩」、すこし後には「大名田堵」)が台頭しはじめ、郡司とその官庁郡衙の機能が衰退していきます。郡司がいなくなる訳ではありませんが、郡衙は消えます。
たとえばこれは東大寺の古文書からでしょう、竹内理三の『武士の登場』-農村の変貌p102 にこう言う事例があります。
九世紀も半ばをすぎたころ、伊賀国名張郡に藤原倫滋(ともしげ)というものがあった。かれはもとは名張郡とは隣り合わせの大和国宇陀郡の住人であった。たまたまその祖母にあたる浄村姉子(きよむらのあねのこ)から、伊賀国名張郡中村などにある畠一町余と在家・所従・牛馬などとをゆずられた。この女性は伊賀国の大目(だいさかん:国司の四番めの官)吉田理規の後家であるから、この畠や在家も夫の遺産であろう。夫の吉田理規が伊賀国の下級国司であったから、吉田理規自身すでに私営田経営者であったわけである。浄村姉子が外孫の藤原倫滋にゆずった所領は夫の遺産の一部であろう。
さて倫滋は、祖母から所領をゆずられたのを機会に宇陀郡から名張郡に移住した。おそらくかれは、それまで所領らしい所領を持っていなかったと判断される。
この藤原倫滋は畠一町余から後に5ヶ村の領地をもつ私営田経営者になります。前のページで竹内理三からの引用での伊賀国の私営田領主藤原実遠とはこの藤原倫滋の私営田を引き継いだ者です。武士の発生についての俗説に「これに対抗するため農民達は武器を持って武装し」と言うのがありますが、その「農民」の実体はこれです。国衙(税務所?)からすれば「税を納めるべき百姓」ですが、浄村姉子も藤原倫滋も後にその土地を受け継いだ猫恐(ねこおじ)の大夫こと藤原清廉(大蔵丞・五位)、藤原実遠(左馬允)も農業経営者ではあっても、農民の出ではありません。
朝廷はまだ律令制を堅持していこうとしますが、実際に国を経営する国司は、そういう現実の変化を無視出来なくなり、いわば実質律令制の規制緩和が地方からはじまります。(これについては「坂本賞三の王朝国家体制論」でまた触れます。)
私営田経営者・私営田領主
ところで、「私営田経営者」という言葉が出てきました。
一般的には「私営田領主」と言います。石母田正の造語だと思うんですが、違うのかな?
私は竹内理三流に「私営田経営者」で通していますが、石母田正が「私営田領主」と言うとき、歴史の発展の中で、中世的な領主制の萌芽、領主制の最初の形態、というような思いを強烈に込めて「私営田領主」と言う言葉を使っているように思います。
私がこのシリーズを書き始めた4〜5年前は、まだ石母田正の『中世的世界の形成』とか、その周辺の議論を読んでいなくって、どうも「領主」という語感と「私営田」がしっくりこない。それで竹内理三にならって「私営田経営者」という言葉を使ったのですが、未だに「初期領主制論」は苦手です。「奴隷」か「農奴」かなんて、「日本における中世の発見」以来の、西洋史での中世の概念下敷きに議論されてもどうもピンとこないんです。それに階級闘争史観を匂わせる言葉が沢山出てくるし。家父長制も素人の私には解ったような解らないような言葉だし。という訳で、「中世的な領主制の萌芽」を全否定するというほどではなく、単に「領主かどうか俺にはようわからん」という意味で「私営田経営者」ということにしています。
私営田経営者は、稲穀(とその倉)、牛馬を資本として持ち、農耕機具を準備し、国衙(県庁)から耕地を借りて、農民を雇い(その賃金のことを功食(こうじき)料と言います)、潅漑用水などを整えて耕作させ、秋にその全収穫を経営主が収納して、耕地の賃借料でもある税金・租庸調の「祖」や、雇った農民の人頭税分である「庸調」を国衙に納めて(いわば源泉徴収)、残りは全部自分の純利益というその名の通りのいわば直営農園経営を行います。
しかしそれと同時に、私交易、つまり物流や商社のようなこともやって、公民(口分田を耕す自営農民)が「庸調」として納めなければならない絹布や、その地方の特産品などを安い時期に買い付けて、自営農民の代わりに国衙に代納し、自営農民からはその収穫時に代納した「庸調」の分として利益を上乗せして請求します。更に私出挙(しすいこ)と言って、田植えの為の稲を貸し出し、収穫のときに高い利息(法的には上限利率100%)とともに取り立てるという、よく言えば銀行機能、悪く言えば高利貸もやり、それによって周辺農民まで支配下におくという経営方式です。平安時代初期に編纂された説話集『日本霊異記』に私出挙に関するこういう下りがあります。郡司の妻なので公出挙のことかもしれませんが。
田中広虫女は、讃岐国美貴郡の大領(郡司)小屋宮手が妻なりき。富貴にして宝多し。馬牛・奴婢・稲銭・田畠あり。うまれながらに道心なく、貪欲にして給与することなし。出挙の時は小さき斤を用い、大きなる斤にてはたり収む。利息を強いてはたること、いとはなはだし。
9世紀の公営田・私営田
同じ方式を「官」がやったものが「公営田」です。
実は資料的にはこの「公営田」、特に823年に大宰大弐(だいに)小野岑守(みねもり)の建策によって大宰府管内で行われた公営田の経営形態などが先に知られていて、そこから、それ以前に民間で広く行われていた方式だったんだろうと推測されて、「私営田」という概念が出来たんではないでしょうか。
大宰府の公営田については阿部猛『日本荘園史の研究』収録の「弘仁十四年の公営田制について」に太政官奏の原文と研究史がまとめられています。以下はここでのテーマに関係ある部分だけをマンガ的に丸めていますが、本当と言うと徭丁(ようてい:農業労働者)の年間実働日数は30日だけで、この公営田からの給料だけで食っていた訳ではないし、これだけの規模を「富豪の輩」を排除して出来たとはとても思えないのですが。
小野岑守の建策による大宰府の公営田計画は大規模で、大宰府管内9カ国から1万2千町の良田を選び、6万人もの徭丁(ようてい:つまり農業労働者)を直接給料制(功食料:こうじきりょう)で雇って耕作させ、収穫から給料も含めた必要経費を除いた分を国の収入にし、減少しつつあった財源を確保しようというものです。もっとも完全直営ばかりではなく、請負方式も合わせて採用していたようですが。
今気がついたのですが、これは初期荘園と同じ方式と考えればつじつまが合うかもしれません。徭丁(ようてい:農業労働者)の年間実働日数が30日だけだったことも。
その計画書の中には、農民からの調庸(ちょうよう:手工業生産物)の収取は考えていません。農民が口分田を耕す自営業だから租庸調の取り立てが生まれるんであって、この経済特区みたいな制度では農民(労働者)は給料を貰っているだけです。これはもう口分田とはまったく違った方式ですね。もちろん朝廷には一定の祖調庸を納めなければなりませんが、調庸はこの直営田の上がりの中から、交易によって調達したようです。計画では祖調庸を納めた後でも108万0421束(よく解りませんが5万石ぐらい?)の収益があがるはずだったそうです。
「国司は律令法を守っていては任国を治めることが出来ない」と、出来る国司は創意工夫で、柔軟に任国経営に当たったというその一例と言っても良いでしょう。大宰府の公営田計画はあまりにも大規模でしたから国解で太政官府に承認を得ようとしましたが、もっと小規模なやりくりは表沙汰にはせずにやったのだろうと思います。「私営田経営」は、太政官レベルではこの時期には律令制の口分田の建前の後ろに隠れていて、公然と認知はされていなかったはずです。菅原道真や三善清行がブツブツ言っていても、それはまだ少数意見で、朝廷全体としては藤原時平らが「世の中が乱れてきたのは律令制を疎かにしているからだ!」と延喜式なんかを編纂していた時代です。
「公営田」も実態は良く解りませんし、対する民間の「私営田」はそんなに画一的ではなくて、経営実態には色んなバリエーションがあるようです。それに、私営田経営をやっていた、「田堵負名」は私出挙(しすいこ)を直営農場以外に対して行っています。ということは、零細自営農民がそれなりに居たということになりますね。9世紀のこの時期は、まだ口分田も旧来の郡司、郡衙もそれなりに残っていて、その中で「私営田経営」が次第に増えている段階、とりあえずはそう考えておけばよいと思います。まあ、当たらずとも遠からじというぐらいで。
公営田にしても、全国くまなくそうなったという訳では決してなく、実態不明を含めても813年(弘仁4)の石見国で30町、873年(貞観15)の筑前国950町、879年(元慶3)の上総国(規模不明)、876年(貞観:じょうがん18)の薩摩国10町、同壱岐島の100町、885年(仁和1)の信濃国30町、942年(元慶3)の畿内5ヶ国の元慶官田4000町などほんの数例のこと。大宰府のものも、いつまで続いたのかどうかは良く解りません。
名(みょう)と負名(ふみょう)
負名というのは税の徴収方式の中での位置づけです。
口分田の崩壊から税の徴収が旧来の形ではうまく管理出来なくなってきて、公田の一定範囲を「名」とし、その範囲の税の徴収をそのあたりの富豪層に請け負わせるというものです。ですから「負名」とは「名田(みょうでん)徴税請負人」というような意味ですね。
なんせ建前は律令制ですから田畑は私有地ではなくてお上のもの。地方においては国司が管理するものですから、負名はあくまで「徴税請負人」。しかし国司の目的は滞りなく税を集めることですから、請負わせる相手は徴税代行者として実力も財力もある者となる訳で、そうなるとその土地の「富豪の輩」ということになります。
そしてその私倉を正倉と認めて収穫した稲を保管させ、前は郡司・郡衙がやっていた田植えの為の稲の貸し出し(出挙:すいこ)もそこからさせて・・・、となって、それまで収穫した稲を保管していた郡衙はいらなくなって消えてしまったという訳です。
学問的には里倉負名(りそうふみょう)とか途中の段階もあるんですが、例によってネグってしまいます。
ここでは「私営田経営者」と「田堵負名」とは、実態としては区別していません。ただ、厳密に言えば、同じ人間が「私営田経営者」であり、かつ「田堵負名」であったとしても(大抵はそうですが)、「私営田経営者」としての経営耕地と、「負名」としての徴税請負範囲は必ずしも一致しません。というのは大和国大田犬丸名などは、ひとつの名の中に複数の経営体があった様です(坂本p137)。もちろん複数の「名(みょう)」に跨る「私営田経営」は沢山あると思います。
ここでの「名(みょう)」は、11世紀以降に出てくる所領とも言える「別名(べつみょう)」とは別物です。
坂本賞三によると、「名(みょう)」が徴税単位として出てくる資料上の初見は932年(承平2)の差押に関する丹波国牒だそうです。そこにでは、「これから名(みょう)を徴税単位とするぞ」ということではなくて、「昔からそうだった」と言っているんです。どういう話かというと、余部郷には口分田が無く、そこに住む者には他の郷の口分田を班給しており、余部郷の調絹はその耕作する口分田がある百姓名(みょう)から徴収するしきたりであったが、その名(みょう)について国衙に登録されていた二名の負名が逃げ隠れして納めようとしないので、各稲200束を差し押さえた」というものです。(坂本p140)
ここですね、「当郷調絹為例付徴郷々堪百姓等名」、木村茂光の口語訳によると、「当郷の調絹は、例として郷々の堪百姓らの名に付徴」。
ところで「堪百姓らの名」という中の「堪」てなんでしょう。
「堪」=能力主義?
木村茂光は2004年版 『日本史講座3−中世の形成』 に納めた「10世紀の転換と王朝国家」の中で、「「堪」=能力主義の採用」という章を設けています。9世紀後半から、「身分や位階にとらわれずに、事に従事する能力をもつ者を任用する」という例、政策がかなり確認されるようです。例をあげればこのように。
-
837年(承和4):諸国講読師
-
869年(貞観11):新羅海賊に備える「夷俘」の長、山陰諸国の弩師(どし:いしゆみの操作者)
-
891年(寛平3):「索盗」に「諸司官人武芸に堪える者」の動員(「西宮記」巻12:源高明によって撰述された有職故実・儀式書)
-
881年(元慶5):諸社の祝部(はふりべ、今で言えば末社の神主さん?)
とそこまではなんらかの職能についてで、それで出世するというなら能力主義なんですが、本人が望んでいなくとも出来そうなやつに命令してやらせるって迷惑な場合も。例えば律令制下では不課戸(課役負担免除)であったはずの勘籍人(例えば僧籍にあるとかで課税を免除された人間)でさえ、「事に従うに堪うべき輩」は「公役」に従わせよ、なんて官符までありますから、名指しされた方は「そんな殺生な!」かな? もっとも、三善清行の「意見封事一二箇条」によると、僧は課役を免れたことから「天下の人民の2/3は剃髪している」なんて状態だったようですから、「ずるして逃げようったってダメだぞ」ってぐらいかもしれません。・・・おや、それも違いますねぇ、これは私度僧になって課税を逃れようとした貧乏農民のことではなくて、さっきの932年(承平2)丹波国牒に出てくる「郷々堪百姓」の平秀と勢豊の二名のことでした。自分の税金のことじゃなくて、あるエリアの人頭税「庸・調」の納税代行者じゃないですか。
もっと積極的なのはこちら。
10世紀の933年(承平3)「非常赦判」(非常赦は特別な恩赦)には「流刑百姓」の口分田を寄作するものがいない場合は「国、堪者に充て行い、殊に営作せしめ」るという政策が採用されているそうです。これは田を耕作する希望者がいなければ、出来そうなやつを選んでやらせてその田の分も年貢を納めさせろって訳ですかね。でもこの「堪者」って、当時の状況を考えると、「おしつけられちゃったよ(泣)」と、自分で鋤鍬をもって出かけて行って、「は〜、残業だぁ、これじゃぁ過労死しちまうぜ」なんでぼやくサラリーマン、いや、自作農民ではなくて、「お前の会社の請負分にこれも追加!」と、あんまり美味しくない仕事まで押しつけられた中小企業の社長さん、あるいは「仕様変更!」と言われたソフトウエアハイスみたいなもんでかね。
かようにしてこの「堪百姓」の採用、というか活用が国衙行政の中で始まって行きますが、どうもこの「堪百姓」って、有能なお百姓さんてイメージではないですね。「堪」は、「その任に堪えられる」で、「武芸に堪える者」なら武芸に秀でた者って個人技能ですが、「納税に堪えられる者」となると、それは稲倉を持つ資産家しかありえません。
「堪百姓」、「富豪の輩」、あと田堵負名、大名田堵、私営田経営者、それらは概ね同じ実態をさしている場合が多いように思います。私営田経営者には王臣子孫がかなり多いので、「堪百姓」のイメージに合わない場合もありますが、百姓=納税者と見れば不思議ではありません。
富豪層論
戸田芳実は1959年に発表した論文「平安初期の国衙と富豪層」(『日本領主制成立史の研究』収録)で前述の史料、932年(承平2)の丹波国牒について触れています。
戸田は、差押え(検封)を受けた2名はかつては「帳外浪人」であり、東寺の大山庄に流れ着いて庄預となっているので、自分の営田を持っている(私営田経営者)ことは間違いないだろう。差押え(検封)の対象となるような蓄稲を持っており、「堪百姓」と言われる裕福な農民であることは上記の国牒で明らか。
更に別の文書に「調沽買絹」とあることから、納めるはずであった、それまで何年も納めていた調としての絹は、その郷にある口分田を耕作していた農民から渡されたものではなくて、売買行為で調達したものであること。つまり耕作農民からは「調」の分として稲等を徴収しておいて、実際に国衙に納める絹は農民から徴収したよりも安い価格で調達して差益を得ていたのだろうと推測します。823年の太宰府の公営田と同じですね。それらの考察から戸田芳実は以下のように述べます。
初期の国衙領における「名」は、富豪層による私営田・私交易・私出挙(特に代納債務関係)を構造的に内包した収取単位であって、その経営者である富豪層を請負人として国衙が慣習的に指定し、制度化することによって成立した。この「名」は、歴史的には階層分化によって進出する富豪層の反律令制的な諸活動のもたらした社会的変動を反映し、それに対抗して非律令的な国例を立法化しつつ支配を維持した国衙の新政策の所産である。したがって、それが直接に土地所有や農業経営と一致しないのは当然といわなければならないが、しかし、それゆえにこれを権力者の側からだけ説明しようとするならば、古代から中世への社会変革過程の表現としての「名」の意味をとらえることができないと思う。(p39)
この論文の為でしょうか、「富豪層論」は戸田芳実の代名詞みたいになりました。しかし最近この「富豪層論」に関して、気になる記述を見つけてしまいました。峰岸純夫が『中世の合戦と城郭』p9 にこう書かれているのです。
武士というのはどこから来たのか。少々難しい議論になるが、そのひとつに、かつて戸田芳実によって提唱された富豪層論といわれる説がある。富裕な農業経営者がいて、彼らが富みを蓄積して力をつけ、武士化していくというコースである。しかし私はそれに必ずしも賛成できない。
峰岸純夫は戸田芳実と面識が無い訳では決してないし、私などよりよっぽど深く読み込んでいるはずの世代の方ですから、何でこういう言い回しになるのか良く解らないのですが、少なくとも峰岸純夫が示した戸田芳実の『日本領主制成立史の研究』(1965年)では、武士の発生に関して、農民が富みを蓄積して力をつけ、武士化していくというなんていうことは一言も書かれてはいません。上記の引用部分では、まるで戸田芳実が武士在地領主論を唱えていたみたいにも読めますが、富豪層論は武士論ではありませんし、戸田芳実はむしろ武士職能論の立場の方です。
ただし、富豪層論は封建制のなかから中世の領主制がどのように生まれてきたかの論であり、平安末期、鎌倉時代の在地領主が、どのような社会の構造変化の中で、どのような変遷を辿って成立していったのかを、その前段に絞って論じたものでもあります。
ところで、上記の峰岸純夫の文章を要約したとき、「富裕な農業経営者」をわざと「農民」とすり替えました。この時代の歴史にさほど詳しくない人はそう読んでしまうだろうと思うからなんですが。
堪百姓は農民か
では富豪層=富裕な農業経営者は農民から生まれたのか。富豪層は当時の言葉で言うと「富豪の輩」「堪百姓」です。というと「ほら百姓でしょ、やっぱり農民じゃないか」と思われるかもしれませんが、その当時の朝廷や国司にとって、「百姓」とは「納税者」ぐらいの意味です。ではその富豪層になった者達は何者? ということになります。それについて戸田芳実は前述の論文「平安初期の国衙と富豪層」(『日本領主制成立史の研究』収録)の4章「王朝公民への展望」をこう書き出しています。
平安時代の諸国衙が、自らの国例をつくって収取の対象として再編成しようとした相手は、「頗有資産可堪従事之輩」すなわち富豪層であり、土浪貴賤を論ぜずという方針で臨まなければならなかったのは、富豪層の多くが、下からの道と上からの道によって中央の官衙や勢家に結びついた肩書きを有し、本職をはなれて諸国部内で活動しながら課役をのがれて律令公民でなくなった者、当時の国衙による表現で一括すれば「浪人」に他ならなかったからである。
つまり口分田を与えられて田を耕していた農民の中から「富みを蓄積して力をつけ」た者ではなくて、それも含めてではあろうけど、社会全体がグラグラと揺れて、かつての国造以来の地元の名士や、郡司や、貴族や官人社会からも大勢振り落とされた、でも口分田を耕していたただの農民よりは資本もコネも知識もあった連中とかが、いっしょくたにシャッフルされて、その混沌としたなかから、農業経営(当時の言葉でいうと勧農)に長けた者、更に今で言えば金融やら流通やらにも才があって富を蓄積して力を付けてきた連中。と、こう考えた方があたらずとも遠からじ。
田を耕していた農民からとだけ考えたらハズレ。とまあこんなところでしょうか。
「負名」の項で触れた「932年(承平2)の差押に関する国牒」に出てくる「堪百姓」平秀、勢豊の二名は三善清行が「意見封事一二箇条」で、課役を免れる為に「天下の人民の2/3は剃髪している」と言った私度の悪僧、つまり正規の僧ではなく、勝手に僧を名乗っている「帳外浪人」と思われますから、農民の生まれだったのかもしれませんが、同時に東寺の庄園の庄預が勤められるぐらいには教養もあったということになります。
もうひとつ。この時代の「堪百姓」、「富豪層」の財産とは田畑ではありません。平安時代初期の説話集『日本霊異記』に見える富の表現は土地よりも稲を備蓄したあまたの屋倉、奴婢、牛馬などの動産です。平安時代後期の『今昔物語集』になると、「領したる田畠」が財産のメインになってきますが。律令制の崩壊は、かつて思われていたような、土地の私有化の進展によるものではなさそうです。
2009.9.16-20 追記